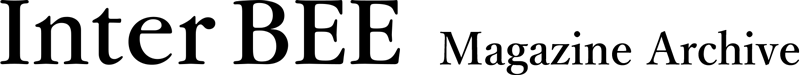【インタビュー】アカデミー賞5部門受賞作 映画「ヒューゴの不思議な発明」 VFXスーパーバイザー ロブ・レガト氏インタビュー(1)
2012.3.9 UP
(写真2)
(写真3)
(写真4)
(写真5)
2月26日(日本時間2月27日)に行われたアカデミー受賞作品の発表会で、 マーティン・スコセッシ監督の新作『ヒューゴの不思議な発明』(原題『Hugo』)がみごとに5部門(撮影賞、美術賞、視覚効果賞、録音賞、音響編集賞)を受賞した。VFXを多用した映画はなかなか作品そのものの受賞にはつながらない傾向にあるようだが、そういったVFXに対する偏見を覆してくれたといえるだろう。本作品のテーマは映画の“魔術”。VFXの原点にあたるものがストーリーの主軸と深く関わってくる。そして、巨匠スコセッシ監督と共にこの壮大なテーマに挑んだのは、ジェームズ・キャメロン作品などで知られるVFXスーパーバイザーのロブ・レガト氏。この絶妙なコンビは、VFXというものの原点を見つめ直すと同時に、立体3D映画の新境地を切り開いたともいえる。今回は、ロブ・レガト氏とのインタビューを通して、本作品における映像マジック制作の舞台裏を2回にわたり紹介したい。(倉地紀子)
★★★★★★★★★★★★★★★★
『ヒューゴの不思議な発明』
3月1日(木)よりTOHOシネマズ有楽座ほか全国ロードショー!(3D/2D同時公開)
配給:パラマウント ピクチャーズ ジャパン
(c) Paramount Pictures 2011
★★★★★★★★★★★★★★★★
■ジョルジュ・メリエスのオマージュがふんだんに盛り込まれた映画
映画は、1930年代のパリを舞台に、13歳の少年ヒューゴの視点を通して展開する物語。伏線となっているのが、20世紀初頭に活躍した映像作家、ジョルジュ・メリエスの半生だ。
マジシャンから映画制作に移行したメリエスはすでにこの時期、ストップ・モーションや初期のSFXに相当する表現技法を映像制作に導入し、数多くの画期的な映画作品世に送り出していた。しかし、第一次世界大戦の勃発と共に姿を消し、その後長く忘れ去られることになる。原作の小説の中でも、メリエスに関するストーリーはほぼ実話に相当するものとなっている。スコセッシ監督も、特にこの部分に大きな感銘を受け、映画化を思い立ったようだ。
それだけに本作品では全編にわたって、メリエスへのオマージュともいえるような、映画の“魔術”を思わせる映像が多数登場。なおかつこれらを21世紀の今日ならではの映像マジックとして実現したところに、本作品の映像の醍醐味があるといえる。
このような特殊な映像的特長をもった作品を支えるためには、VFXにおいてもさまざまなチャレンジが必要とされた。中でもレガト氏が強調するのは、立体3Dという新たな要素への対応と、実に多岐に渡るVFXの方法論を同じアート・レベルのもとで一つに統合することの難しさだった。
■「13歳の少年の記憶にあるパリ」を映像化
本作品では現実の世界の特定の時代について、時代考証なども含めてリアルに描写することは求められていなかった。
たとえば、映画に登場するCGのパリの街。これを制作するために、その当時のパリのあらゆる写真や絵画がリファレンスとして用いられ、それらをベースにして街のモデルやテクスチャが作成された。しかし、実際に監督が望んでいたものは、どれ一つとして1930年代のパリに実際に存在した道路や建物ではないのだ。
なぜなら、監督が望んだこの街の映像は、13歳の少年の視点から見たもので、大人の目から見たものとは大きく違っていなくてはならなかったのだ。描き出さなくてはならないのは、あくまで「13歳の少年の“記憶”の中に残っているパリの街」である。ストーリー上の要請も含めて、多くの面でリファレンスに見られる1930年代のパリをモディファイする作業が必要とされた。
イメージベーストや雪のシミュレーションなども含め、きわめてテクニカルな表現技法を駆使しながらも、究極の目的は、現実の世界のリアリズムというよりも、むしろ卓越したアート作品の作成というにふさわしいものであった。
ストーリー展開の要となっている機械人形も、実寸大の模型が作成され、この模型が多くのシーンで活用されたが、きわめて重要なシーンでは、模型からCGバージョンに置き換えられている。
主人公ヒューゴの亡き父が残した機械人形は、物語が進行するにつれてヒューゴの分身と化してゆく。単なる“メカニカル”な機械人形としての存在を超え、“暖かみ”のあるキャラクターとして表現するために、CGバージョンが活躍しているのだ。
CGバージョンでは、機械人形の情緒的な表現を克明に行うために、ライティングを変化させたり、CGの機械人形のサーフェースの形状やテクスチャに細かい変化を加えることで、機械人形の見え方を微妙に変化させている。
映画後半ではヒューゴの夢の中で、この機械人形がヒューゴの体とオーバーラップし、ヒューゴの体の内部に内臓のように埋め込まれるシーンが出てくる。ここではヒューゴの身体もCGで作成されている。監督はこのヒューゴの”肉体“にも、どこか“機械人形”に通じる風情をもたせることを強く望んでいた。CGのヒューゴは最終的には、デジタルダブルではなく、アート的な視点から様々な様式化を加えたものとなっていたそうだ。(デジタルダブルとは実写の俳優をCGでそっくりそのまま復元したものを指す)
【写真説明】
(写真1)
真剣な表情でモニターを見つめる、VFX Supervisorのロブ・レガト(Rob Legato)氏(画面左端)
(写真2、3)
『ヒューゴの不思議な発明』には、初期の映画エフェクトへのオマージュを思わせるシーンも多数登場する。“紙ふぶき”のエフェクトは、メラニスが自ら作成した映画の中で“蝶”をイメージして用いたエフェクトへのオマージュだ。ポスターにもなっているヒューゴが時計にぶら下がっているシーンは、ハロルド・ロイドの『ロイドの要心無用』(1923)へのオマージュとされている。
(写真4、5)
亡き父の形見ともいえる機械人形。動かぬ機械人形を “修理”することが、13歳の少年ヒューゴの“ライフワーク”だった。スクリーンに登場する機械人形には、模型のものとCGのものがあり、CGバージョンの機械人形はヒューゴの分身にあたるようなオーガニックは風情をもっていることが望まれていた。このためCGの機械人形では、模型の機械人形よりも、サーフェースやテクスチャのディテールがさらに細かく造り込まれていたという。
(写真2)
(写真3)
(写真4)
(写真5)