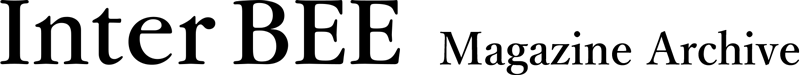【インタビュー】アカデミー賞5部門受賞作 映画「ヒューゴの不思議な発明」 VFXスーパーバイザー ロブ・レガト氏インタビュー(2)
2012.3.9 UP
(写真2)
(写真3)
(写真4)
(写真5)
((1)より続く)
★★★★★★★★★★★★★★
『ヒューゴの不思議な発明』
3月1日(木)TOHOシネマズ有楽座ほか全国ロードショー!(3D/2D同時公開)
配給:パラマウント ピクチャーズ ジャパン
(c) Paramount Pictures 2011
★★★★★★★★★★★★★★
■最新のCG技術と従来のVFXの発送をうまく組み合わせる
本作品には少し古風なVFXのアイデアを最新のCG技術とうまく組み合わせたものが数多く登場する。その代表例といえるのが、公安官が機関車に足を挟まれて引き摺られてゆくシーケンスだ。軽快なギャグとして好評を博したこのシーケンスは、レガト氏お気に入りのシーケンスでもある。
ここでは、機関車は静止させたままで、公安官が立っているプラットフォームをトラックの上に載せて動かしながら撮影が行われた。このアイデアは古くから用いられていたもので、かつてレガト氏がVFXスーパーバイザーを担当した『タイタニック』でも導入されたそうだが、この時には地面にあたる部分がスクリーンに映し出されることはなかった。
今回はプラットフォームもスクリーンに映し出されるのだが、撮影時にトラックに載せられているプラットフォームの模型は俳優の周辺だけの小さなものだった。したがって、最終的にはこれをCGで置き換えて、スクリーン上に40フィートにもおよぶ長いプラットフォームを映し出すことが可能となった。
背景もプラットフォームと同じ速度で動くようにCGで作成されている。『タイタニック』以降の10年余りのCG技術の進歩はやはり大きく、俳優の思いつきから始まったというこのギャグ・シーケンスが瞬く間に完成したゆえんもこのあたりにあったようだ。
■スコセッシ監督の独自の映像スタイルを実現
上記のように、『ヒューゴの不思議な発明』の映像制作では、高度な技術と背中合わせで、常にアート的な視点による表現を積み重ねることで、スコセッシ監督が望む独自の映像スタイルを実現していった。このような姿勢は、立体3Dという新たな要素への挑戦にも反映された。
立体3D映画は2D映画にプラスアルファで新たな要素を加えるという考え方が主流だ。そのため、撮影・後処理の両面でさまざまな工夫を求められている。『ヒューゴの不思議な発明』においてもその考えは同様だった。本作品では、特にシーンのムードやトーンをダイレクトに左右するような場面において、立体3Dの表現が登場するため、そのできばえが作品全体に大きな影響を与えることになり、制作工程の特定の段階で何かを加えるというだけではすまされなかった。
レガド氏はそうした、作品の大きな山場で立体3Dが使われたシーンの一つとして、線路に降り立ったヒューゴとの衝突を避けようとした機関車が脱線するシーケンスを挙げている。
脱線した機関車は大きな窓を突き破り、駅の建物を破壊して、階下のパリの街へと落ちていく。機関車が窓を突き破る瞬間のショットでは、機関車の一部や窓の実寸大の模型が撮影されているが、その他の場面では機関車も駅も吹き飛ぶカートも、さらには火花や煙といったエフェクトもすべてCGで制作されている。
映画の中でも最も”VFXヘビー”なこのシーンでは、まず、どのような表現や方法論が効果的かを知るための丹念なプレビジュアライゼーションから始められた。いうまでもなく、このプレビジュアライゼーションは立体3Dでおこなわれている。
この機関車の脱線シーンは、映画の中に2度登場する。1度目はヒューゴの夢の中で、2度目は現実として、映画の中に2回登場する。ストーリー展開上でも、1度目のシーンのインパクトを観客の心に強く残し、2度目のシーンを目にした観客に「夢が現実となった」ことを強く意識させること、さらに「夢が現実となる」シーンが再び登場するのではないかと期待させることが非常に重要だった。
そのような効果を狙って、1度目のシーンのどの部分を再現するか、どのデーターを再利用するかといった判断をする上でも、上記の立体プレビジュアライゼーションは非常に大きな意味をもっていたのだ。そして、このプレビジュアライゼーションをもとにしたシーケンスの作成では、列車のようなメイン・オブジェクトから吹き飛ばされる小さな破片や塵にいたるまで、アニメーションのあらゆる瞬間において立体3Dを生かすための作業が繰り広げられたという。
■アーティストが手作業で手掛ける立体3Dからflameを駆使した「立体ロトスコープ」へ
それは、特定の作業をプログラムなどによって自動的に付加するといったようなものではなく、個々の瞬間で個別の判断が要求されるアーティスティックな作業に近いものであったそうで、レガト氏はこれを初期のカラー映画の制作に例えている。その時代、スクリーン上の彩色(coloring)はまさにアート・クラフトといえるものだった。「今の立体3Dはこれと同じなのだ」と同氏は語る。
スクリーン上の彩色は、技術の進歩に伴ってアーティストの手によっておこなわれていた初期の段階から、アーティスト以外の人の手でもおこなわれるようになった。同様に、今回のプロジェクトでは、立体3Dに関してもこうした進化を感じさせる新たなテクニックが考案されている。それは、flameを活用した“立体ロトスコープ”のワークフローだ。
映画中盤には、若き日のメリエスが映画制作をおこなっているシーンが登場する。そして、このシーンのメリエスを表現するためには、メリエスを演じたベン・キングズレーを若返らせる必要があった。骨格を大きく変えたり筋肉を大きく変形させたりするほどの必要はなく、“デジタル・コスメティックス”に相当する程度のものだった。しかし、若きメリエスが登場するシーケンスは、尺がかなり長い。非常に多くのフレームをトラッキングして“デジタル・コスメティックス”を施したメリエスを埋め込む必要があった。
従来のように2Dの状態でこのエフェクトをおこなっておいて、後処理で立体3Dに変換しようとすると、特にコンポジットの作業が非常に複雑で手間暇のかかるものとなる。そこで今回は、最初から立体3Dの状態でトラッキングをおこなってデジタル・コスメティックス”を施したメリエスの顔を埋め込むという方法がとられた。
手順としては、まずベン・キングズレーの顔の3Dメッシュを作成し、撮影プレートのトラッキング・ポイントを、片方の目からベン・キングズレーの顔の3Dメッシュ上に射影する。次に、このようにトラッキング・ポイントをあてがわれた顔の3Dメッシュをflame上に読み込んで、正確な瞳孔間距離だけ離してもう片方の視点を設置する。左右両方の視点から見て整合性がとれるように各フレームのトラッキング・ポイントの位置をアップデートすることによって、結果的に立体3Dのトラッキングがおこなわれることになる。
危惧されたのは両目からトラッキング・ポイントの位置をアップデートする作業の煩雑さだが、ある程度のノウハウを得ると意外なほどスムーズに作業をおこなえるようになるという。同時に位置のアップデートがほんのわずかであっても、実際にそれをおこなった場合とおこなわなかった場合とでは、最終的に3Dメガネをかけてスクリーン上で観た時の見え方がかなり違うということもわかったという。
作業スケジュールの短縮という意味でも、立体3Dに対する理解を深めたという意味でも、このワークフローの考案は非常に意義深かったといえそうだ。
■メリエスが生み出したエフェクトをCGで実現
レガト氏は、上記のワークフローについて「本プロジェクトで用いられたあらゆる技術の中で最も誇りに思う」と述べている。理由はまず非常にシンプルであること。「シンプル・イズ・ベスト」は、VFXの作成において往々にして“真”なのだという。そしてこの一つの同じ方法論で、映画に登場するあらゆるタイプのメリエスを確実に“若返らせることができるという汎用性も高く評価している。もちろん、そこには新たなステージに向かいつつある立体3D技術への期待というものもあるようだ。
立体3Dの効果は、若き日のメリエスが登場するシーンでも活用されている。古い映画のグレインや紙ふぶきのエフェクトなどはその一例だ。またここでは、当時メリエスが生み出した映画エフェクトの数々が、最新のCG技術を用いて再現されているところも大きな特徴となっている。
レガト氏にとって、この作業工程は非常にエキサイティングなもので、同時に実に多くのことを学ばされたという。VFXは映画における映像の魔術に他ならないのだが、そこで一番大切なのはやはり“アイデア”だとレガド氏は語る。まずは“アイデア”から始まり、次にそのアイデアにどのようにして生命を吹き込むかという方法論を考える。
方法論にしても、決して新しければよいというわけではない。時代を経て受継がれてきた技術にはそれなりの良さがある。その一方で、新たに登場した技術に置き換えられて姿を消していく技術もある。それゆえに、各時代において用いられる方法論の集合体は常にアップデートされていく。「これらの集合体をうまく一つに融和させることこそが、映像のマジックなのだ」とレガト氏はいう。
そして、その事実はメリエスの時代からまったく変わっていないのだ。ちょうどメリエスがマジシャンから映画制作者に移行していったように、映画が2Dから3Dへと移行していくのもごく自然な成り行きといえるのかもしれない。この新たな“魔術”の次なる展開への期待に、レガト氏自身も大きく胸を膨らませているようだ。
(倉地紀子)
【写真説明】
(写真1)
映画の中で、ヒューゴの宿敵ながらも味わい深い役柄となっている“公安官”。
軽快なギャグとして好評を博したのが、この公安官が機関車に足を挟まれて引き摺られてゆくシーケンスで、公安官を演じる俳優みずからのアイデアであったという。ここでは、機関車は静止させたままで、公安官が立っているプラットフォームをトラックの上に載せて動かしながら撮影をおこなうという比較的古風なVFXの手法と、最終的にはプラットフォームも背景もすべてCGで置き換えるという今日ならではの高度なCGテクニックが併用された。
(写真2、3)
列車の脱線事故は、実際に1895年にパリのモンパルナスの駅で起こった事故がモデルとなっている。したがって、駅の光景はこの当時のモンパルナス駅の写真を参考にして復元された。画像のシーンはセットだが、事故のシーンの駅は、立体3Dならではの効果を大きく意識して、すべてCGで作成された。
(写真4)
立体3Dの効果は、列車の脱線事故のような動的なシーンだけではなく、静的なシーンでも生かされている。監督が望むアート性の高い映像スタイルにうまくマッチした立体3Dの効果をつくりだすためには、撮影時や後処理の特定の工程で一度につくりだすというよりも、複数の工程で細かい処理を何度も重ね合わせて最終的な立体3Dの効果をつくりだすという方向性がとられていたようだ。
(写真5)
初期のSFXに相当するものを20世紀初頭にすでに実現していたのがフランスの映画制作者ジョルジュ・メリエス。『ヒューゴの不思議な発明』の中で名優ベン・キングズレーが演じるのは年老いたメリエス。若き日のメリエスを表現するためには、撮影プレートのベン・キングズレーの顔を、立体ロトスコープのテクニックを用いて、デジタル・コスメティックスによって若返らせたベン・キングズレーの顔で置き換えるという作業がおこなわれた。
(写真2)
(写真3)
(写真4)
(写真5)