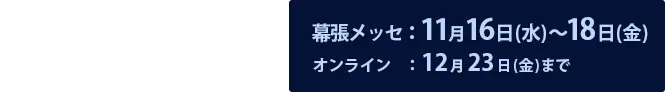【INTER BEE CINEMA】クリエイターズインタビュー 浜根玲奈「チャレンジする環境によってアップデートされる”働き方改革”。育児と仕事の両立の秘訣はNYで学んだ分業ワーク!」
林 永子

Inter BEE開催60回目を記念して特設された【INTER BEE CINEMA】。エリア内では、実際に建て込んだスタジオセットにて撮影を行うライブショー、著名なゲストを招いたトークセッション、選りすぐりのシネマレンズの装着や解説を行う「レンズバー」といったユニークなコンテンツとともに、映像制作者の交流や若手育成を促進する場を3日間にわたって提供した。
この「クリエイターズインタビュー」では、今後も続く【INTER BEE CINEMA】の取り組みにつなぐべく、映像クリエイターのオリジナリティ溢れる活動歴とともに、多様な表現活動を行う「人」にフォーカスした記事を掲載していく。
今回のゲストは、2000年代の日本のデジタルクリエイティブを牽引したteevee graphicsにて若手作家としてスキルを磨き、2010年代後半はNYを拠点とした新たな活動にチャレンジした浜根玲奈監督。現在は、広告、テレビ番組、イベント映像など幅広いジャンルの映像制作に取り組みながら、一児の母として育児と仕事を両立する彼女に、その秘訣と経緯について伺った。
プロフィール

浜根玲奈
Reina Hamane
⽇本⼤学芸術学部在学中、モーショングラフィックスに興味を持ち、卒業後はteevee graphics, incに参加。CM / MV / Webムービーなどの演出・実写編集・モーショングラフィックスなどのノウハウを学ぶ。2012年に独⽴、ディレクター・モーションデザイナーとして活動を開始。クリーンな実写と洗練されたモーショングラフィックスを組み合わせた表現を得意とする。2016年New Yorkに移住。Brand New School、Slanted Studios、Adolescent などのクリエイティブスタジオでフリーランスモーショングラフィックスデザイナーとして数々のプロジェクトに参加後、2020年より拠点を⽇本に移す。現在はアメリカと⾏き来しながら活躍の場を広げている。日英バイリンガルで、資生堂、Amazon、Panasonic Beautyなどの国内外の広告案件や、グラフィック広告のアートディレクションを行う他、NHK Eテレ「デザインあ」のコーナーやクラッチも担当している。
https://www.kirameki.cc/artists/reina-hamane/
下積時代の挫折と青春の紅白歌合戦
――まずは映像を志した経緯から教えてください。
高校生の頃からコンピュータが好きで、母が買ったWindowsのPaintというソフトでお絵かきをして遊んでいました。その延長線上で、放送やデジタル系のクリエイティブで何かできないかと考えて、日本大学芸術学部に入学したんです。当時、周りの学生はFinal Cutで編集していましたが、私はもう少し踏み込みたくて、After Effectsを愛用していました。
――編集というよりも合成に興味があった?
どちらかといえば。サークルをつくって撮影する学生も多い中、私は映画や演技よりも、モーションの方に興味がありました。当時は情報が少なく、一言でMotion Graphicsといっても、よくわからないけれども幾何学図形が動く映像、みたいなアバウトな認識でした。希少な海外のWEBサイトにはPSYOPやTOMATOといったクリエイター集団の名前が書かれていて、日本のteevee graphicsやCAVIARのお名前を最初に見た時も、海外のチームだと思い込んでいました。かっこいい集団がいるなと、漠然と憧れているイメージでした。
――その憧れから始まって、制作プロダクションでの1年間の勤務を経て、teevee graphics入社。最初はアシスタントから入られました。
最初は、もう、本当に大変でした。大学の頃に私が触っていたAfter Effectsの知識や技術は、赤ちゃんレベル。先輩の谷篤さん、長添雅嗣さん、田辺秀伸さんはとにかく優秀で、自分は彼らが大学1年生の頃にクリアしていたレベルよりも全然下だと感じて、衝撃を受けました。20代はずっと苦しかったです。何度もやめようかなと考えました。
――それでも踏みとどまって、学び続けた。
当時は、会社に寝泊まりして、徹夜で詰めるような、下積の期間があって、私の場合は5、6年経験しました。ある意味では、学びの良い機会ではあり、対人関係のマナーやCGの発注先の方に失礼のない対応などについても教わりました。その点、売れている先輩たちはしっかりしていて、いい先輩につけたのは本当にラッキーだと思います。
――初めてディレクションした作品について教えてください。
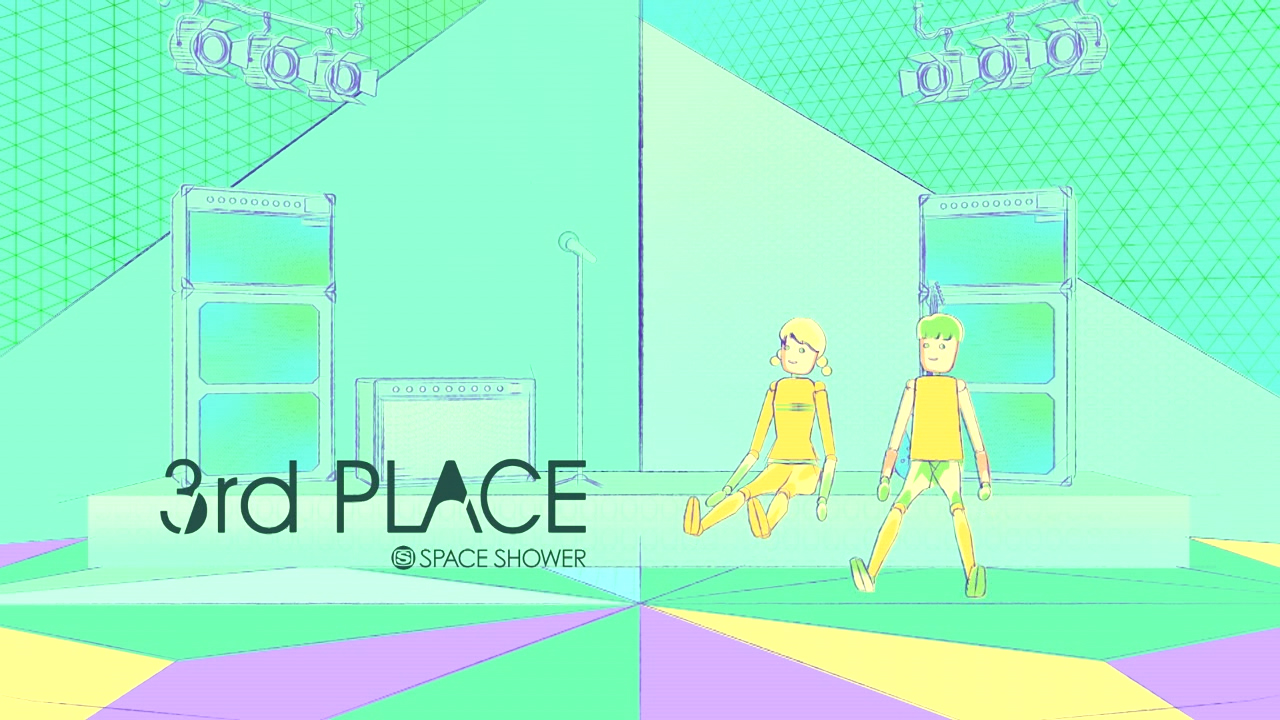
スペースシャワーTVのStation IDです。音楽専門チャンネルのStation IDは若いクリエイターたちの登竜門で、そこから同年代のディレクターたちがどんどんMVに移行していきました。音楽番組のランキングやタイトルバックなども制作するうちに、私自身も少しずつMVを演出するようになっていきました。主にCG合成作品が多く、全工程を自ら制作。3DCGも自分でつくるので時間がかかり、1ヶ月ぐらい家にこもりきりで制作していました。年末のNHK紅白歌合戦の背景映像も、その頃の思い出深い作品のひとつです。
――紅白歌合戦の映像もまた登竜門のような存在でしたよね。

そう。若手はみんな参加していました。本番前に関係者の忘年会に行くと、みんなレンダリング中に抜けてきていた(笑)。そんな状況も含めて、青春みたいな感じ。新しい映像シーンが活性化してきている機運が感じられた時代で、メディアアーティストの真鍋大度さんを筆頭に、熱いクリエイターたちがたくさん関わっていました。プロジェクションマッピングも流行していて、Motion Graphicsが一段階上で世に認知された印象がありました。
――ご自身にとっても良い機会になりましたか。
多くの方に見ていただけて、やりがいがありました。ただし、フルCGの限界を感じた時期でもありました。CGクリエイターは、上には上がいる。そして予算がないからCG合成で、というネガティブな依頼に、疲弊しながら人力で応え続けるにも限界がある。実際にお仕事でも、自分の中でトリガーとなるような作品をつくりきれていない感覚があり、そのままCGを続けても、先細りする未来が見えていた。もっとディレクションに注力して、厚みのある作品をつくれる人になりたいと一念発起して、海外に行くと決めました。
NYで学んだワークスタイル
――2016年、拠点はNYへ。どんなお仕事をされていたのでしょうか。
NY在住のファンタジスタ歌磨呂さんがディレクションしていたMVにCGディレクターとして参加したり、現地のクリエイティブスタジオで、フリーのMotion Graphics Designerとしてさまざまなプロジェクトに携わったり。一番大きな仕事は、Google CESのカンファレンス会場の映像制作。After Effects部門の一員として参加したのですが、これがすごい体験で、一番上にプロデューサーがいて、ディレクター、CG、コンテライター、コンポジットなど、各部署が流れ作業のようにどんどんコンテンツをつくっていく。フロアに100人ぐらいいて、全員モーニングもランチも無料でした(笑)。
――超太っ腹!そして徹底的に分業ですね。
とにかく分業です。あくまでも私が経験した一例ですが、ディレクターが撮影後は編集に立ち会わない場合もあるし、プリプロ段階も、撮影前にクライアントに全カットのアグリーを取り、ほぼ完成が見えた状態で撮影に入ります。撮影後に予定外の修正をかけてきた場合は、追加料金が発生する。ドライな部分もありつつ、クオリティやクリエイティブに対するリスペクトは日本以上に感じられました。

――作品づくりもされていたのでしょうか。
時間を見つけては制作していました。NYは3歩あるけばクリエイターに会う街で、みんな自分の作品をInstagramに投稿していて、名刺がわりに見せ合うんです。MVを動画で紹介するよりも、InstagramでCGのコンセプトなどしっかり明記したうえで一枚絵を見せた方が、反応が良い。クライアントワーク云々よりも、どんな作品をつくる人なのか、フィードでぱっと見てわかるようにしておいた方が、NYでは話が通じやすかったです。日本でも、若いプロデューサーはInstagramでコンタクトを取り始めています。
――そして2019年に一時帰国。残念ながらコロナで再渡米できず。
アメリカと日本の仕事を半々くらいでやろうと考えていて、ビザを更新するために帰国したのですが、戻れず。同時に子供ができたので、しばらく日本にいることに。仕事を続けるにあたって、クリエイティブプロダクション「キラメキ」にマネジメントを委託しました。当初は日本での4年間のブランクとコロナで、仕事が来るか不安になりましたが、妊娠中に参加した「NEWoMan」のトリートメントコンペに勝って、自信がつきました。商品や場所やコピーなどのお題に対し、映像のコンセプトやイメージをまとめたボードを作る。そのトリートメントのやり方をアメリカで学んでいたので、コンペを勝ち抜くことができました。
――帰国後から現在まで、最も記憶に残っている作品について教えてください。

1つは、出産して半年後に撮ったPanasonic Beautyの広告。まだ授乳している時期だったので、スタッフの方にはとてもお世話になりました。初めてのドキュメントタッチの実写広告で、カメラマンはキラメキ所属のオーストラリア人Ivan Kovac。彼は出演者と距離が近く、そこにある空気感をふわっと撮る。外国人のカメラマンは遊びがとても多く、固くなりすぎないところが面白いです。そしてクルーも半分外国の方々だったので、現場が自由な雰囲気で楽しかったです。現場はお祭りなので、ピリつかず、楽しいのがベストです。もう1つは資生堂 アクアレーベルのコマーシャル。こちらはteevee graphicsの小島淳二さんの系譜で、あとに続く夢が叶いました。私の中でトリガーとなった作品です。
育児と仕事、両立の秘訣は分業制
――出産・子育てを経験されている浜根監督ですが、仕事との両立に秘訣はありますか?
アメリカでの経験が役に立っていて、分業制を取り入れています。以前は1人で抱え込んで制作してきましたが、働き方を変えて、全体の構成要素を各パートに振り分け、それぞれのスタッフに指示を出し、ワーク後のパーツをもとに全体を整えていく方法に切り替えています。今の時代、リファレンスが必要不可欠なので、フレームの中のすべてに細かく指示を出し、何度かやりとりしながら齟齬を解消していく。そして早く切り上げる。
――時間配分にメリハリをつける?
お仕事が決まる時に、基本的には17時以降は稼働しないと先に伝えます。海外の効率的な働き方を目の当たりにして、リセットされたのかもしれません。もちろん現実的にはメールやイレギュラーな対応が発生するので、子供が寝た後に夜中まで作業することはあります。が、自分は仕事がある方が、モチベーションがあがるタイプ。子供が2歳になるまでは外界とのつながりがなく、子供と一緒に居る時間が長いのはいいことだけれど、仕事をしなくていいのか、自分ができる仕事はあるのかと、考え込みがちだったのですが、今は精神的にも安定しています。もっとも家族も子育てに協力的で、関わるスタッフのみなさんやマネージャーさんがうまく調整してくださるからこそスケジュールが成立しています。周囲の方々にとても感謝しています。
――環境によって働き方も変わりますね。最近はどんなお仕事をされていますか?
コマーシャルの仕事をしながら、昔からつながりのあるNHKさんの子供番組を演出したり、イベント用の展示映像を制作したり。広告のみにとどまらず、いろいろなアプローチを試みています。
――Instagramに掲載されている、AIのグラフィック作品についても教えてください。

AIの人物写真と描画を合わせて絵にしています。本能的につくってあげていますが、実は、仕事につながるワークでもあります。最近制作予算も下がる中で、一枚絵のカンプのようなイメージを事前に提示すると、完成形が見えてクライアントが安心するという風潮があります。このワークを日々更新していくことが、その訓練になる。日常の観点や思いつきを落とし込んだら、それを見たクライアントが関連するお仕事をくださったケースもあります。
――最後に、<INTER BEE CINEMA>は映像制作者の交流の「場」を目指しています。どんなお話をしたいか、ご意見をお願いします。
バーチャルプロダクションに興味があります。天候や出演者のコンディション、全体的なテンションも含めて、グリーンバックで撮るより自由度も精度も高いし、十年後にはもっと普及しているはず。先日もスタジオに見学に行ったのですが、もっとコンパクトに利用できる未来がすぐに来そうなので、早めに情報を仕入れたいと思っています。