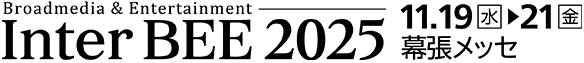Special
2023.01.20 UP
【INTER BEE Curation】メタバース関連展示もさらに加速!「CES2023」で見た“次世代テレビ”まとめ
※INTER BEE CURATIONは様々なメディアとの提携により、InterBEEボードメンバーが注目すべき記事をセレクトして転載するものです。本記事は、Screensに2023年1月19日に掲載された「CES2023」に展示されたテレビモニターをまとめた記事となります。お読みください。