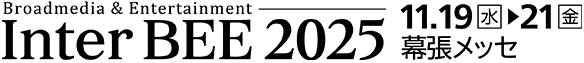Event Report
2025.03.27 UP
【Inter BEE CURATION】アジアのクリエイティブ産業の勢い反映〜香港フィルマート2025現地取材レポート~

香港貿易発展局が主催するアジアを代表するエンターテインメント・コンテンツのトレードショー「香港フィルマート」が3月17日から20日までの期間、香港コンベンション&エキシビションセンターで開催された。参加者数は昨年より上回り、出展した国数も増え、アジアのクリエイティブ産業の勢いを反映していた。会場では業界トレンドのAIソリューションの展示やコープロの話題が盛り上がり、今年はアジア発アニメが主役となる場面もあった。現地取材した「香港フィルマート2025」をレポートする。